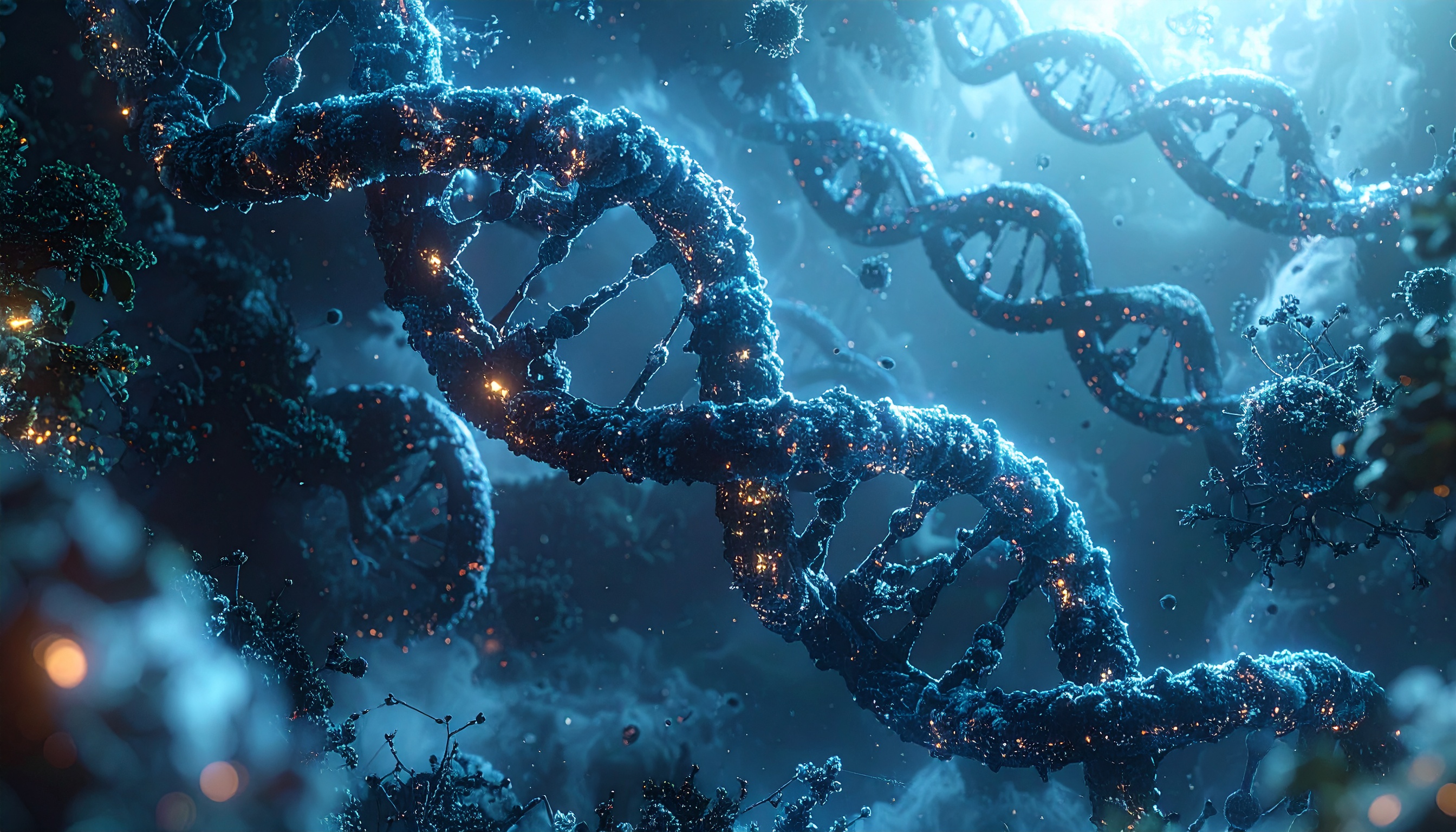本サイトの記事や画像は、AIが公的資料や複数の報道を基に事実関係を整理・再構成し制作したものです。[続きを表示]特定の報道内容や表現を再利用・要約することを目的としたものではありません。ただし、誤りや不確定な情報が含まれる可能性がありますので、参考の一助としてご覧いただき、実際の判断は公的資料や各出典元の原文をご確認ください。[私たちの取り組み]
保険診療で広がった「がん遺伝子パネル検査」が、実際の診療でどこまで患者の予後改善につながっているのかが、大規模データで検証された。国立がん研究センターなどはC-CATに登録された5万例超を解析し、遺伝子異常に基づく治療が一定の成果を示す一方、治療導入が想定より伸びていない現実も浮かび上がった。
5万4185例を解析 未承認薬の標的でも予後改善を示唆
国立がん研究センターと慶應義塾大学医学部は1月8日、2019年6月〜2024年6月に保険診療で実施されたがん遺伝子パネル検査(FoundationOne CDx)5万4185例の臨床ゲノムデータを用い、標的治療の実施状況と患者予後を解析したと発表した。研究結果は2026年1月6日に英科学誌Nature Medicineに掲載されたという。
解析では、治療標的となる遺伝子異常は72.7%で認められた。加えて、国内承認薬の対象となる異常だけでなく、国内未承認でも海外承認やガイドライン記載などで有効性が示される薬剤の標的となる異常が見つかった場合にも、患者予後が相対的に良い傾向が示された。つまり「異常が見つかること」自体が、治験や患者申出療養制度などを通じた治療選択肢の拡張につながり得る、という位置づけである。
導入は8.0%にとどまる がん種差と薬剤アクセスが壁
一方で、検査結果に基づき新たに標的治療が導入された割合は全体で8.0%にとどまった。CBnewsはこの数字を報じ、がん種別では甲状腺がん34.8%、非小細胞肺がん20.3%、小細胞肺がん20.1%が高い一方、膵がん1.3%、肝臓がん1.8%は低いと伝えている。検査時期別には2019〜2020年の5.5%から2023〜2024年に10.0%へ上昇しており、伸びしろはあるものの格差が残る。
国立がん研究センターは、大規模データの利活用により、TMB-highに対する免疫チェックポイント阻害薬の効き方ががん種で異なることや、コンパニオン診断薬が陰性でもパネル検査で陽性なら標的治療が有効となり得る症例がある点も示したとしている。対岸の火事ではなく、C-CAT登録が10万例を超えた日本の基盤を生かし、治験の受け皿拡充や適応外・未承認薬への到達経路を整備できるかが、検査の「見つける力」を「治す力」に変える次の焦点となる。